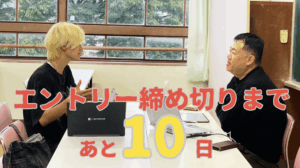メンターが気付きを引き出し、その気づきがプランを磨き上げる~ファイナリストの実例から~ 〜その③〜
事例1:Aさんの挑戦 (セミファイナルからファイナルまでのプランの変遷)
セミファイナル時点のプランは、幼稚園向けに「収穫+調理体験」を販売し、農業参入者でも利益を確保できる仕組みを描いていました。
しかしメンタリングを重ねる中で、根本的な課題は「参入者が農業技能を学べず、定着できないこと」だと気づき、最終的には「農地の貸し手と参入者をつなぎ、ベテラン農家の技能を伝承する仕組み」へと進化しました。
/
メンタリングでの気づき
「体験だけでは技能習得にならない」
Aさん自身が「農業技能の習得には年単位の修行が必要」と実感していたことが出発点でした。そこから、
「じゃあ、修行の場をあなたが提供したら?」という問いが生まれ、ベテラン農家を雇用し、技能を教える仕組みという新しい発想が育っていきました。
「農地マッチング」という新しい視点
「農地を借りてほしい」という相談が参加者のもとに集まっていたことをヒントに、
農地所有者と参入者を結ぶマッチングの場としての事業モデルが見えてきました。
「販路」という最後のピース
参入者・農地・技能がそろっても、販路がなければ規模拡大はできません。
そこでメンターから「地域で廃業した大規模農家の販路を引き継げば?」という提案が。
実際にネギ農家の引退情報とつながり、販路確保の道筋が描かれました。

メンターとの会話の中で
メンター:セミファイナルでいろいろ指摘を受けたわけですが、今は何が気になってますか?
Aさん:農業に参入しても儲からない。その原因が生産技能習得に時間がかかりすぎることなのは確かなんですが、ニンジン収穫体験だけでは解決策にならないんだと気づきました。
メンター:生産技能が身につくまではサービスで稼ごう、という発想は悪くないよ。ただ、それだけやと技能習得につながりにくい。あなたはどうやって生産技能を教わってるの?
Aさん:地域の農家さんたちに教わってます!でも野菜生産も年一度しか経験できないので、ほんとは農家さんに住み込みで修行したほうがいいんです。これは農業に飛び込んでから実感しました。
メンター:なら、農業参入する人はみな、事前に農家さんで修行したらええんとちゃうのかな?
Aさん:見ず知らずの他人をいきなり受け入れてくれる農家さんはいないです~
メンター:ほな、あなたが修行の場を提供したらええやん。
Aさん:わたしはまだまだ修行の身ですよ。農業生産技能を教えることなんかできないです・・・ん?近所のベテラン農家さんが先生になってくれたらうちの会社が農業やりたい人のための学校になれるかも!
メンター:ん?農業技能教える学校は全国にあるで。行政がやってるし。
Aさん:でも、そういう所って実践的じゃないです。私も就農前に調べました。
メンター:ほな、実践的に農業技能を学ぶには?
Aさん:だからベテラン農家さんのところで何年か修行するのが一番です。でもそんな農家さん滅多にいませんもんね・・・じゃあ、私の会社がベテラン農家さん雇用して、私の会社で農業参入者を雇用して、ベテラン農家さんが農業参入者を一から教えたらいいじゃん!
メンター:農地を借りてほしいベテラン農家さんの農地をあなたの会社が借りるやんか。「農地管理をしてあげる」対価と考えると、農地借地代はタダになるかもよ。
Aさん:なら、そのベテラン農家さんに先生になってもらえますね。月10万円くらいでもやってくれそうな人が浮かびます。
メンター:それが成立するなら、あなたの会社が「農地貸借のマッチングの場」にもなるわな~
Aさん:ほんとですね!わたしが抱える課題を解決できそうです!
メンター:あなたの会社の農業生産技能も向上するから、あなたの会社の農産物販売額も伸びるで。
Aさん:うちの売り上げが伸びる分だけ、農業参入者を雇用できますもんね。農地を借りてほしいという話は私の手元にいっぱい来てますし、その農地の所有者が農業生産技能を支えてくれるし、人では農業参入希望者を雇用することで確保できますし。
Aさん:私の会社はこれで、規模拡大のための要素をすべてそろえることができますね!
メンター:ん?ほんまかいな~?もう一つ、肝心なものが足りないよ。販路。
Aさん:うわ~、ほんとだ~。野菜の生産量が増えたら直販では間に合わないですね・・・。
メンター:あなたが営農する地域で大規模生産してる野菜の品目は?
Aさん:ネギが増えてます。あとは、きゅうり、ほうれんそう、さといも、こまつな、ブロッコリー、えだまめあたりですかね。
メンター:なるほど。このなかで高い生産技能を要しないのは、ネギ、こまつな、ブロッコリー、えだまめかな。
Aさん:こまつなは誰でも作れし競合農家が多いです。ビニールハウスも必要。
メンター:残るはネギ、ブロッコリー、えだまめやね。この中で、最近、大規模農家が廃業したとかいう噂を聞いたことないかな?
Aさん:全部あります。あ、それで野菜の卸売業者さんから「〇〇さんがネギ生産やめるから、あなた、やらない?」って声かかりました!
メンター:っちゅうことは、そのネギ生産やれば販路も確保できるがな。
Aさん:ほんとだ~!その話、具体的に交渉します。
メンター:うん、交渉条件を明確にするためにも、そのネギ生産にいくらコストかかって、どれくらい人手や機械が必要かを計算してみましょう。それで成立するなら、このコンペのプランもその方向で描いてファイナルに挑みましょうか。
Aさん:以前、そのあたりは計算したんですよ。ネギを生産する腕さえあればガンガン儲かるんです!この方向でプランを描きます。

プランの進化(Before / After)
| 項目 | セミファイナル(12月) | ファイナル(2月) |
| プラン名 | 「自分で採った野菜は美味しい!」で素人農家が儲かる | 農業の「もったいない」を民間事業で解決 |
| 社会課題 | 埼玉県で農家減少し続け、数年後に地元産野菜が購入困難に | B県には多くの農業参入者がいるのに、数年後に農地面積が半減してしまう |
| 課題の構造 | 農業儲からない⇒後継者不足。農外参入しても生産ノウハウと農地取得困難で定着できない | 農地借りたい参入者と農地所有者のマッチングの場が少なすぎる。そして参入者は農業の技能取得困難 |
| 解決策としての事業モデル | 幼稚園向け収穫+調理食事体験を販売。ニンジンを半分の栽培期間で収穫させることで、生産リスク低下+回転数増加し、利益確保 | Aさんの会社が農家から農地を借り受け規模拡大+参入者雇用し、農地貸主が技能を教えることでマッチングを図る |
| 目指す社会像 | B県農家の収益ポイントが増え、利益を上げやすくなる。それにより後継者が増え、参入者が定着し、地域の野菜生産が確保される | B県では、農地減少に歯止めがかかり、消費者が必要とする地元産野菜の生産が確保される |
| 売上目標 | 年間売り上げ3,700万円 | 年間売り上げ6億円 |
この事例から見えてくる edge の強みについて
edgeの魅力 ― 対話から生まれる成長のプロセス
ソーシャルビジネスプランコンペ edge の大きな特長は、「問いかけ」と「対話」を通じてアイデアを磨き上げていけることです。
メンターとのやりとりの中で、自分の想いや課題の本質が言葉になり、次第に具体的なビジネスモデルへと進化していきます。
たとえば、ある参加者は当初「やりたいことはあるけれど、形になっていない」という段階で参加しました。
メンターからの問いに答えていくうちに、自身の活動の軸や、誰に届けたいのかという対象像がクリアになり、さらに収益の仕組みや実現性についても考えが深まりました。
結果的に、「ただのアイデア」から「実現可能なプラン」へと大きく前進することができたのです。
edgeの場は、単なるコンペティションではありません。
自分一人では気づけなかった視点を得られる合宿やメンタリング、仲間とのディスカッションが、挑戦を後押しします。